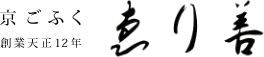夏を愉しむ衣~男性浴衣のご紹介~
6月の中盤から気温が一気に上昇し、7月に入り本格的な夏が訪れました。
京都本店がある四条通りの商店街のアーケードでも祇園祭のお囃子が流れ、お祭りムードに心躍る今日この頃。「祇園祭の巡行の前後で梅雨明けする」…と幼いころから教えてもらっていたので、この時期の梅雨明けには驚くばかりです。
35℃を上回るような気温が続く中で、快適に過ごすための”衣”としての吸湿性や涼感、肌触りなど実用的な意味合いが見直されているように思います。お客様のお話では、今年は男性の方の普段使いとしての麻の甚平さんがよく売れているとか…
夏の衣の代表の一つである浴衣は、弊社では4月から店頭に並び、5月にかけては「ゑり善 大人浴衣ものがたり」としてご紹介してまりましたが、おかげさまで多くのお声がけをいただき、ひとつひとつ丁寧に、でもお召しになられる日に向けて急ぎながらお仕立てを進めさせていただいております。
浴衣からお着物のスタートに…というお話をされるお客様もおられて、改めて浴衣の着こなしが和装振興において重要な意味を持つことを感じております。
さて、今回は「夏を愉しむ衣~男性浴衣のご紹介~」と題して、男性の浴衣の着こなしについて、少しご紹介させていただきます。

●浴衣を愉しみたいと思ったら…様々な選択肢
最近では夏の衣装として浴衣を愉しみたいと思ったときに、選択肢がとても多くなり、手に取りやすいものになりました。
◇ レンタル
なんといっても気軽に楽しめる。使うときだけ。準備やお手入れは不要
◇ 古着で購入
寸法は出来上がったもの。
シミや生地の痛みなどは承知の上で、安価にご自身のものとして愛用できる
◇ 出来上がりの浴衣を購入
標準的な寸法から選択して購入。すぐに着ることができる
◇ 生地から選んでお誂え
こうした選択肢には、それぞれのメリットがありますので、ご自身のお考えに沿って、その中からご選択いただけるとよいでしょう。
その中で、私たち、ゑり善がご提供しているサービスは、4つ目の「生地から選んだお誂え」となっております。
お誂えの特徴としては…
デメリットとしては、
・費用と時間がかかる
・着た後の片付けやクリーニングが必要になる
・保管の場所が必要
一方でメリットとしては、
・身丈・身巾・裄(手の長さ)など、ご自身の寸法にぴったりの浴衣が作れる
・着崩れがしにくく扱いやすい
・いつでも自由に愉しめる
・長く愛用できる
ということがあげられます。
7月と8月の約2か月という限られた期間に愉しむものが浴衣です。お仕立てされるかどうか悩まれるというお方も多いかもしれませんが、祭事や神事、毎年恒例の行事などが多くなるこの季節は、自然と着用機会が増えるもの。このブログがお誂え浴衣の一歩となりましたら、何より嬉しく存じます。
● オーダースーツの感覚で生地に向き合う
さて、男性の夏の浴衣の生地として、弊社がお勧めしている生地には大きく2つの素材がございます。
(1)木綿
インドで古くから栽培されてきた綿。植物のワタからとれる繊維のことを”木”の綿として、木綿と呼びます。
繊維の特徴は「よじれ」があること。この特徴が紡績のしやすさにつながっております。
また、断面図を見ると「中空」とよばれるように内部は空洞になっております。
独特の肌触りや保湿性、吸湿性に優れる点はこうした特徴から生み出されております。
一方で弾力性には乏しく、しわになりやすく縮みやすいという点は、天然のものだからこその特徴としてとらえていただくほうがよいでしょう。
弊社では、竺仙さんの浴衣をご紹介しておりますが、こちらでも染色がしやすい綿の生地が使われております。
はっきりとした紺と白のコントラストなど、粋な印象で柄を楽しむ浴衣として、毎年人気をいただいております。
(2)麻
縄文時代の早い時期には日本の広い地域に生育していたとされる麻。
茎の内側の木質部と表皮の間にある靭皮(じんぴ)から繊維を取り出します。
麻といっても種類は豊富で、亜麻(Linen)や苧麻(Ramie)、大麻などがよく知られております。麻の種類には約20万もあるとか。
独特のシャリ感が特徴で、涼感に富み、吸水性、特に放湿性に優れていることで、夏の代表的な素材となっております。
麻は天然繊維の中でも水にぬれると強度が増すという性質があり、耐久力にも優れているとされています。さりげない光沢はキリッとした着姿を演出してくれます。

無地や縞の柄のものが多いのですが、シンプルで飽きがこないのが魅力の一つ。お手入れも比較的、楽にできるのも特徴です。弊社のスタッフにも人気な訳はそこにあるように感じております。
生地や色合い、また柄や縞の幅によって印象はがらりと変わります。オーダースーツのように、生地に向き合い、是非お顔にあてていただきながらご自身のお好みの様子を見つけてくださいませ。
● 和裁の妙。寸法の考え方
お誂えの浴衣の醍醐味の一つはご自身の体形にあった仕立て。弊社ではお仕立てに際して、主に3つの部分を採寸いたします。
◇ 身長と身丈
男性の身丈は着付けによって調整ができない分、この寸法はしっかりと確認させていただきます。場合によっては寸法見本を羽織っていただくことも。同じ身長でもご体形によって変わりますし、お好みもございますので、しっかりとご相談いたします。着用して移動も多くなる(階段なども含めて)こともあるので、若干浴衣の身丈は短めにすることが多いです。なお、綿や麻など生地の変化による縮みも考慮します。
◇胸囲・ウエスト・ 腰回りと身巾
胸囲やウエスト、腰回りのサイズは、着物の身巾を考える際に大切な箇所になります。洋服のスラックスようにボタンをつけるわけではないので、多少の変化は受け入れてくれるのが着物の良さ。細身の方でもあまり極端には狭くしないほうが生地への負担を減らすことができます。
◇ 裄 手の長さ
手の長さから裄を決めます。おしゃれ着でもある浴衣においては、あまり長いと動きにくく、ドアノブなどにもひっかけてしまうことも。ご要望を伺いながら決定します。
その他細かな点はお客様にご確認いただきながらひとつずつ決めさせていただきます。お任せいただくことも多いですが、ご希望やお手持ちで着やすい寸法などがあればお知らせいただくことも大切です。
体形の変化や着付けの仕方などにより少しずつ変わっていくものが寸法の考え方の一つ。最適なご寸法を見つけていけるようにお話をさせていただきます。どうかお気軽にご相談くださいませ。
弊社ではお着物のお仕立てをしてくださっているお仕立て屋さんにお願いをし、1枚1枚手縫いで仕上げていただいております。そのため、お仕立てまでには約1か月から1か月半ほどお時間を頂戴しております。
● 浴衣も着物も同じ?着付けに関する ちょっとしたポイント
男性の着付けは実にシンプル。ですがその分奥が深いもの。慣れが一番ではございますが、今日は3つだけポイントをお伝えさせていただきます。
(1)帯の位置「おなかの下とおしりの上」
男性の着姿において、最も目立つと思われるのは帯の位置ではないでしょうか。
意識していただきたい姿としては、「前はおなかの下、後ろはおしりの上」ということ。
横から見た姿として、少し前下がりになっているほうが恰好がよくなります。歩いたり座ったりすると、帯はどうしても上がってきてしまいます。
気づいたときには、おなかの前の帯びに、上から親指を入れて、「帯を下げる」を意識していただくことをお勧めします。
(2)帯の結び目は美しく
帯の結び方には種類はたくさんございますが、一般的に人気な結び方は「貝ノ口」とよばれるものです。
この形においてとっても大切なことは、結び目をきれいに整えておくこと。着物は背中で見せる衣装でもあります。
くしゃ…となった結び方にならないように、丁寧に注意して結ぶようにしてみてください。
(3)衿がはだけないように
最後に「襟元」の大切さです。
紐で止める箇所がすくない男性の着物はその着付けの方法からして衿がどうしてもほどけやすくなっております。肌着などが見えると…あまりきれいにはみえません。
その点、おすすめなのは、「衿止め」とよばれるもの。衿あわせにとりつける着付け道具になりますが、つけてしまうと外からは見えません。
かがんだり動いたりしても衿が崩れないすぐれもの。衿が崩れてしまって…と気にされる方にはご使用をおすすめします。
以上、今回は男性の浴衣についてご紹介をさせていただきました。
暑い夏がいよいよ始まりますが、活動的な夏を過ごすための衣として、浴衣が皆様の夏の思い出の中にあれば何より嬉しく存じます。
どうかご相談などございましたら、京都、銀座、名古屋店各店舗までお気軽にお尋ねくださいませ。
ゑり善 主人 亀井彬

![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)