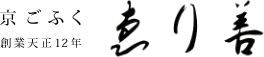「反物」から「着物」に~手縫いの技術~

珍しく雨の降った前祭の巡行に、炎天下のもと行われた後祭の巡行。
お天気に負けずに鉾を曳かれた方々、巡行に参加された方々勇姿に四条河原町も盛り上がりを見せておりました。
祇園祭に向けて浴衣をお仕立てされた恵理子さんたちもお祭りを楽しまれたことでしょう…
さて、そちらの「大人浴衣ものがたり」でもちらっと出ておりました仕立ての場面。
手縫いの良さや柄の出し方の工夫についてお話しさせていただきましたが、今回はもう少し深掘りしてご紹介いたします。
お着物の仕立て方、をお伝えするには私もまだまだ知識が足りませんので、基本的なところから手縫いの魅力について知るためのポイントを中心にお伝えさせていただきます。
ゑり善では新人社員を対象に、8月に夏季研修を行っております。
以前も成果報告を兼ねて絞りの技法についてご紹介させていただきましたが、昨年は仕立屋さんにもお話を伺ってまいりました。
今年の研修も約1か月後に迫ってまいりましたので、その前に昨年の研修の振り返りを兼ねてお話しさせていただきます。
〈きものの仕立てについて〉
~キーワードその1『つまり』~
仕立ての世界は経験が要だといいます。
生地の縮みやすさなどの状態を見極めながら、それぞれの生地に合わせて縫う強さや糸のひっぱり具合を調整していくからです。
経験を積むために、生地を知るためにまずは生地をまっすぐ縫う練習からはじまるそうです。
最初に木綿と木綿、それができるようになったら木綿と絹を縫う練習へすすみます。違う素材はまっすぐ縫うことが難しくなります。これは素材によって生地の縮み具合である「つまり」具合が異なるからです。つまりを見越して、余裕を持たせた縫合わせが必要になるのです。
様々な生地をまっすぐ縫えるように練習しながら生地の特徴、きれいに縫うための工夫の仕方を知っていきます。
~キーワードその2『地の目』~


お洋服もお着物も生地を裁断して縫い合わせて…というのは同じですが、お着物の最大の特徴はまっすぐに裁断していくことです。
「地の目を通す」とよくいわれますが、織り上げられた生地をよく見ると糸の通り具合がみえるのがわかるでしょうか。この糸のまっすぐな線である「地の目」を、目を凝らしてよく見てそれに沿って裁断していきます。
~キーワードその3『運針』~
一反のお着物を仕立てるためには約60メートルから70メートルの糸が必要になります。
基本の縫い方、というと並縫いを思いつく方も多いのではないかと思いますが、並縫いでは多大な時間がかかってしまうため、和裁では「運針」と呼ばれる縫い運びが基本となります。
針の先を親指と人差し指で挟み、中指にはめた指ぬきで針の底を押しながら、親指で針を下げて人差し指で針をあげます。それに連動させて反対の手は生地が針と直角になるように上げ下げしていきます。
文字だけですと伝わりづらいと思いますので、気になる方は動画など調べてみてくださいね。
この縫い方は着物をほどくときにほとんど跡がつきません。
時間効率が良いだけでなく、仕立て替え可能な着物に合った縫い方なのです。
〈ここは注目してほしい!仕立てのポイント〉
続いては仕立て上がったお着物でもぜひここは見てほしい!という箇所をお伝えします。
~袖丸~

直線美のお着物のなかにある曲線部分、袖の丸みの部分。
袖丸はまず段ボールのような厚紙にコンパスで丸を書いて型を作り、それに沿って着物に印をつけ、印を基準に丸く縫っていきます。細かい縫い方は割愛させていただきますが、ひだを作りながら縫い、縫った糸を引っ張ることで丸に仕上がるそうです。
ひだを均等に、中に縫い込まれる部分が重ならないように縫えるほど、綺麗な曲線に仕上がるといいます。


ちなみに、袖丸は通常5分(半径2cm)ほどの丸みになりますが(写真 紫の着物)、丸みが大きいほどかわいらしい印象になりますので振袖などは袖丸が大きくお仕立てされています。
浴衣などのカジュアルなお着物でも袖丸を大きくして違いを出すのも楽しいのではないかと思います。
~裾~
裏地のついた冬物、袷のお着物は八掛という裏地が少し表から見えるように仕立てます。(写真 着物の濃い色の部分)
このように仕立てることで、八掛がお着物の裾を擦り切れから守ってくれますし、ちらっと見える色の違いもおしゃれですよね。
このとき出す長さはまず目分量で合わせます。縫うときも指先の感覚をたよりに糸のひっぱり具合などを微調整しながらまっすぐ、均等な長さで仕立て上げていくそうです。
では裏地のつかない単衣や夏もののほうが仕立てるのは簡単なのかというと実はそうでもないらしく、表地(着物の生地)だけで仕立てる単衣や夏のお着物は、歩くときの裾さばきなどによって裏の部分がみえることがありますので、裏側まで綺麗に縫えていることが必須なのです。
「裾を見たら上手下手が分かる」と和裁士さんが仰っておりました。
角がピンと立った褄先の部分もご注目です。


…と、袖丸・裾部分を挙げさせていただきましたが、お着物の仕立ての良さがこれだけで決まるわけではないと仕立部社員も言います。
お蚕さんから作られる糸で織った絹の反物は生き物です。温度や湿度の影響を受けやすく、生地の状態やお天気によってもコンディションが異なってくるそうです。日によって変化する生地の状態に合わせて縫い方を調整できるのは手縫いだからこそできることです。
地道な練習と努力を重ねて生地を理解し、時間が経っても綺麗な状態のままのお着物でいられるように逆算して縫い合わせていく。お着物を作る技法を知るたびにその奥深さに圧倒されますが、仕立ても例外ではありません。
仕立屋さんはお召しになる方の顔がみえず、寸法という数字からしかお客様を知ることができません。お客様が着心地よくお着物をお召しになることができるように、どのようなご用途でお召しになるのか、どのような着方をされる方なのか、伝えるのは私たちの役目です。
同時に、橋渡し役として皆様にも仕立屋さんのかけがえのない技術を知っていただきたく、今回仕立てについてご紹介させていただきました。
まだまだ伝えたいことはたくさんありますが、それはまたの機会に。
「まっすぐ縫う」ことを基本としながら、仕立て上がったら見えなくなるところまで気を抜かずに数々の工夫をして、ひとつのお着物を仕立ててくださる仕立屋さんの細やかな配慮を知っていただけましたら幸いです。
本店営業・久保田真帆
![京ごふく ゑり善[創業天正12年]](https://www.erizen.co.jp/wordpress/wp-content/themes/erizen/img/common/logo_pc.png)